叶匠寿庵
和菓子、洋菓子を問わず、高級なお菓子は自分のためにはなかなか買えないので何かのタイミングで入手できた時は思わず記録に残してしまいます(笑)。というわけで、今回は、今年の正月にいただいた叶匠寿庵(かのうしょうじゅあん)の代表銘菓「あも」とそのバリエーションである「あも(栗)」を取り上げます。
 |
| 叶匠寿庵 あも あも(栗) |
まずはあもを製造販売している叶匠寿庵について調べてみると...株式会社叶匠寿庵(匠壽庵)は滋賀県大津市大石龍門に本社を置く企業で、1958年(昭和33年)9月に芝田清次氏が滋賀県大津市の長等(三井寺の東)にて菓匠「叶 匠壽庵」(現在の長等総本店)を創業したことに始まります。
公式ホームページによると、その事業内容は和菓子の製造・販売、茶室・茶事(懐石料理と茶席)、一般飲食事業(喫茶・甘味処)となっており、北海道から福岡県まで百貨店を中心に計72店舗を展開しています。1985年(昭和60年)3月には大津市大石龍門に「寿長生の郷(すないのさ)」をオープンし本社工場を移転しました。この寿長生の郷は自然豊かな丘陵地にあり、面積は63000坪。菓子作りの原点は農にありという「農工一体」の思想を取り入れ、里山の風景をそのまま残して梅や柚子など約800種の植物が植えられているそうです。

そんな叶匠寿庵が1971年(昭和46年)に発売し、今も同社のロングセラー商品となているのが「あも」です。
●叶匠寿庵 公式ホームページ →https://kanou.com/
あも
叶匠寿庵の代表銘菓として人気のあもは、和菓子の中でも棹菓子に分類されます。棹菓子とは長方形の棒状の菓子で、代表的なものに蒸し羊羹があげられます。格の高い菓子とされ、贈答に用いられることが多く、通常は包丁で切り分けて提供されます。
 |
| 「あも」と「あも(栗)」 |
商品名の「あも」とは、かつて宮仕えの女性(女官)たちが使っていた女房言葉で「餅」を指すそうです。やわらかい印象の女房言葉の例として他に、お寿司は「おすもじ」、饅頭は「おまん」など、紹介されています。しおり
 |
| 内側の包装紙 |
包装紙には商品名の他に「丹波大納言小豆」と記されています。
 |
| 型紙を開いた状態 |
開封すると、小豆の粒がぎっしりと詰まった羊羹のような和菓子が登場します。
 |
| たっぷり小豆と求肥 |
断面を見ると、たっぷりの小豆を使った餡の中に「餅(求肥)」が入ったシンプルな和菓子であるこがわかります。
丹波大納言小豆は味と香りが良く、皮が薄くて口当たりも素晴らしい小豆として知られていますが、全国収穫量のわずか1%という希少な小豆です。あもには発祥の地である丹波の中でも春日地方(現兵庫県丹波市春日町)で収穫される最高品質の小豆「春日大納言小豆」が使用されています。この小豆を丁寧に仕込み、じっくり蜜漬けした後、こだわりの手炊きと糸寒天で仕上げているそうです。
また、小豆に包まれた求肥は羽二重餅で、口の中でほどける小豆と同じ柔らかさに仕上げられています。
小豆の絶妙な甘さと香り、求肥の食感などが見事に調和した逸品といえます。
あも(栗)
あもには様々な素材と組み合わせた期間限定の商品が数種類あり、今回は「あも(栗)」をいただきました。秋から冬にかけて登場する季節限定商品で、包装紙の毬栗が目印となっています。
 |
| あも(栗) |
あも同様にあも(栗)もたっぷりの高級小豆が使用されていて、一見見分けがつかないように思われます。
 |
| しっかりと栗が見える断面 |
しかし、断面を見るとスイーツ界では秋の味覚ともいえる栗が羽二重餅に煮えり込まれていることがわかります。こちらは通常のあもに、モチっとした食感の中に栗の歯ごたえと風味が活かされた、まさに秋にふさわしいあもに仕上がっています。
1971年の誕生から50年迎えたあもですが、2012年から塩、白小豆、土鍋あん生あも、柚子、桜、蓬、紫蘇、抹茶、胡桃、栗、令月あも(梅酒)、あも歌留多、こしあんなどのバリエーションが登場し、今でも季節限定などで販売される商品もあります。
●詳しくは公式ホームページ あも →https://kanou.com/gnaviplus/item/amo/
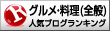
コメント
コメントを投稿